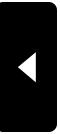昨日に続き、薪の玉切り。
1/3くらいは終わったかなぁ、、、という感じです。ようやく。
それにしても、木は重く、切っていくだけでも大変なのに、運び、積み上げる大変さ。想像以上です。
残りを切って、さらに割らなきゃならないなんて、、、。
薪ストーブを入れると決めて、ショールームへ見に行って、気に入ったストーブを見つけて、、、。
薪つくりも楽しみながらやればいいや!って思っていましたが、その境地に達するのは少々時間がかかりそうです。
楽しんでやる。
そのためには、一気にやろうと思わないことが肝要なんでしょう。
やると決めたら一気に!なんて思っていましたが、時間があるときに、怠けて緩んだ体を動かすぐらいのつもりでやろうっと!
でも、昨日と比べると、玉切りの薪は少し増え、ナラの原木は少し減ったかな。